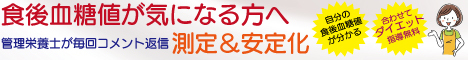堀井憲一郎vs桂宮治
みなさん、こんにちは。
ブロガーのすい喬です。
数日前、コラムニストの堀井憲一郎が落語家、桂宮治のことを書いてました。
とにかくたくさん落語を聞いている人です。
ぼくの手帳には彼が1年間寄席で聞いた落語のトップ100が貼り付けてあります。
数年前、創刊40年を迎えた日本で唯一の寄席演芸専門の情報誌『東京かわら版』に載ったものです。
ちなみにトップは「子ほめ」166回とあります。

2位は「時そば」の147回。3位は「初天神」の126回です。
これだけ落語を聞いている人は、それほど多くはないでしょう。
ラジオにも出てますので、声をきいたことがある人はいるかもしれません。
とにかく落語好きであることに間違いはないのです。
その彼が新進落語家について書きました。
笑点への抜擢以来、宮治の周辺は大変な賑やかさです。
これだけ一気に知名度を上げた人は、それほどいないでしょうね。
その落語についていろいろと書いていたので、つい読んでしまいました。
新宿末広亭での2月、「桂宮治主任公演」の話が発端です。
無念なことに桂宮治はコロナのみなし陽性となってしまいました。
7日目から4日間だけの出演となったのです。
その時の様子を見事に報告してくれています。
宮治は座布団に座らずに下手の端まで行って、そこにあるスタンドマイクを片手に、「2階席っ!」「桟敷っ!」「アリーナ!」と声を掛けて盛り上げた、とあります。
目に見えるようです。
実は以前から何度もぼくの所属している落語の会にも来てくれました。
その時の姿が彷彿としたからです。
それくらいのことなら、いつでもやる噺家です。
家にいた時間が長い分だけ、ぶつけたいものがたくさんあったんでしょう。
とんでもない熱気
桂宮治は、立ったまま、喋り続けたそうです。
15分以上のマクラのあと、落語は「手水廻し」を。
その後、堀井憲一郎は宮治がとんでもないところに到達しそうだと予言しています。
彼の言葉を借りれば「かつて見たことのない場所」にたどりつくのではないか、という畏るべき存在に思えるというのです。
1番最初に会ったのはまだ前座の時でした。
酒の席で、そこにいた人たちの酒をついで回る役でした。
自分を可能な限り抑制しているのがよくわかりました。
安定したいと言ってましたね。
その目を今でもはっきり覚えています。
会の中に今でも中心的な彼のタニマチがいます。
名前を出せば、誰もが知っている人です。
真打披露のパーティへの出席はもちろん、寄席もほぼ全て通い詰めたのです。

ぼくも勧められて、NHKの新人落語コンクールへ行きました。
あの時の熱狂はすさまじかったですね。
放送ではカットされましたが、賞金に対する熱望のようなものを感じました。
あのような席でお金のことを口にするのはかなり珍しいのではなかったでしょうか。
二ツ目に昇進したのは2012年のことです。
春に昇進して、秋に新人演芸大賞を受賞しました。
しかし当時の歌丸会長はだからといって特別扱いはしなかったのです。
そういう意味で、香盤を崩す考えは全くもっていませんでした。
14~15年のキャリアがなければ真打にしないということだったのです。
二つ目の最初に賞を取り、「成金」というユニットの中でも年を取っていながら、若手の役割を負うというのは苦しかったはずです。
腐る予感
あの頃、宮治は今の境遇に我慢できるかという話をした記憶もあります。
本当なら、かなりの勢いで笑点のレギュラーもねらえる位置にいたのです。
まだ早すぎるということも確かに言えます。
しかし芸人は囃されたら踊るというのが鉄則です。
ものすごい努力をしていました。
とにかく覚える噺の数がすごい。
どんどん吸収していきましたね。

真打披露の楽屋の様子も見事でした。
その前に同じ協会の神田伯山も楽屋の様子を次々とアップしました。
その上をいったのが宮治です。
とにかくすごい真打披露でしたね。
多くの先輩芸人が駆け付けました。
関西からも来てくれたのです。
鶴瓶などはよほどのことがなければ、顔は出さないでしょう。
ある意味「人たらし」の要素を持っています。
敵をつくらない。
腰の低さは定評があります。
しかし眼は笑っていません。
修羅を背負う
堀井憲一郎の今回の文章で1番感心したのが次の内容です。
——————————-
お笑いのおもしろい第一線に十年以上いつづける芸人は、おもしろい人でありながら、やがて修羅を背負ったような雰囲気を出していくようになる。
ライブで身近で見てるときにかぎり、一瞬だけ凄まじい気配を放つのを感じることがある。
大笑いしている観客をすっと肌で鋭く測っている。
そういう動物的な気配である。
——————————

この部分には舌を巻きました。
芸人の根性の底の底にはこの感覚が必要です。
これがなくては一流になれません。
さて今後はどうなるのか。
目が離せませんね。
いつか枯れていくのか。
賑やかなままなのか。
芸人の生きていく先は誰にも見えないのです。
今日はここまで。
じゃあね。