芸は砂の山
みなさん、こんにちは。
ブロガーのすい喬です。
すぐれた芸人の残した表現には、心に残るものがいくつもありますね。
「芸は砂の山」がそれです。
これは六代目三遊亭圓生が生前よく口にしていた言葉です。
唐突ですが、ぼく自身の経験を少しだけ書かせてください。
今年で落語を話し始めてから15年が過ぎました。
最初の頃は、覚えるのが楽しく、それを聞いてもらうのも、すごく嬉しかったです。
ところが、馴れてくるにつれ、うまくいかないことが増えました。
以前ならお客様に受けていたところが、これといった笑いもなく、サラリと過ぎてしまうのです。
これは考えすぎかもしれません。
取り越し苦労と言えないこともないのです。
そんなにたくさんの高座をつとめているワケでもありませんしね。
確かなことは言えないです。
もちろん、圓生師匠のように子供の頃から楽屋に出入りして、高座にあがっていた人と比べることなんて無論できません。

プロには覚悟があります。
どんなことがあってもこれで食べていくというという厳しさが、ついてまわるのです。
それは確かにその通りなのです。
ぼくのは芸などと呼べるようなものではあれません。
ただの遊びです。
最近実感としてよくわかるようになりました。
高座にあがるのも、たかだか年に10回くらいのものです。
1番多い時でも20回ぐらいではなかったでしょうか。
それでもやっぱりプロの噺家と似たようなことを感じるのです。
このあたりが芸の怖さでしょうか。
マンネリの怖さ
高座はもちろん、稽古で少しでも楽をしようとすると、すぐに自分の芸がずるずると落ちていくような気がしてなりません。
本人はそれでも一生懸命やっているのです。
しかしいつの間にか、緊張感がなくなり、間が変化しているのかもしれないのです。
フランスの作家、アルベール・カミュの著作に『シーシュポスの神話』というのがあります。
日本風にいえば、シジフォスの神話でしょうか。
御存知ですか。
神を欺いたことで、シジフォスは怒りを買ってしまい、大きな岩を山頂に押して運ぶという罰を受けます。
彼は神々に言い付けられた通りに岩を運ぶのです。
しかし山頂に運び終えたその瞬間に、岩はまた転がり落ちていってしまいます。
それをまた運ぶ。
つまり人間はそういう不条理に耐えつつ、生きているという譬えなのです。
崩れていくのがが芸というものの本質だといわれれば、そんなものかと思わずにはいられません。
必死になって上っていく。
あるいは積み上げていけば、なんとか前と同じ状態をキープできるのではないか。
またお客様に笑ってもらえる。
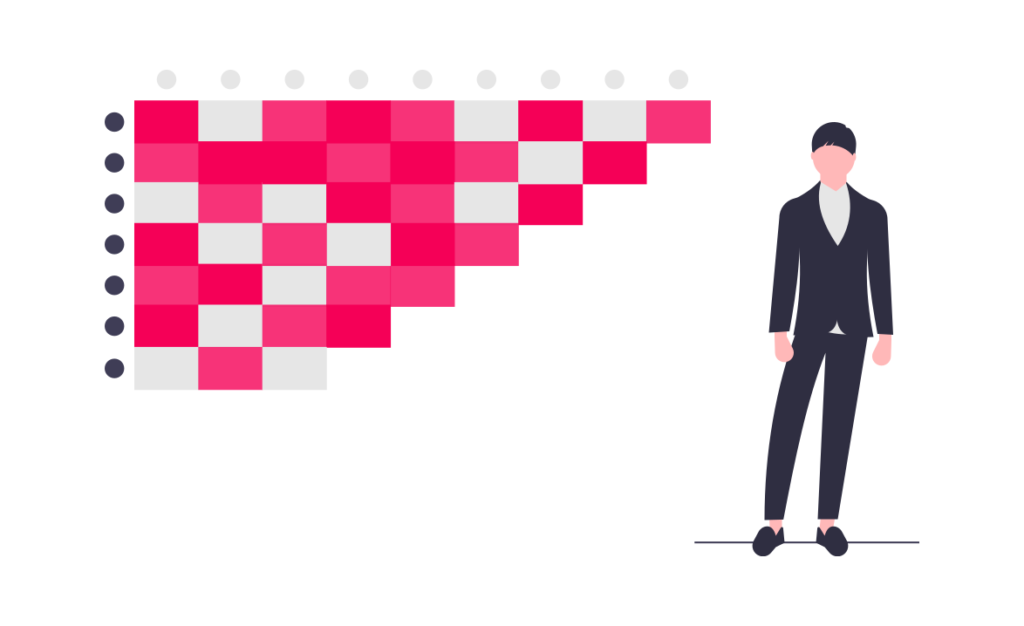
晩年の林家三平もそうでした。
最盛期は高座にあがっただけで、爆笑の渦でした。
それがいつの間にかどんなにお客をいじっても、誰も笑ってくれなくなったのです。
別に手を抜いたワケではないでしょう。
芸が動かなくなると、面白くもなんともないのです。
お客様が演者に飽きたら、その場で噺の命はなくなるのは当然のことです。
演者自身が噺に飽きても同じことが起こります。
重い言葉です。
それだけ新鮮さを保ち続けるということは、並々でない修練を必要とします。
圓生はどこでもぶつぶつと一人で稽古をしていたそうです。
これだけ稽古をした人はいないと、弟子たちは声を揃えて言います。
古今亭志ん朝にも似た話がありますね。
いつも二階でひとしきり必死になって稽古をしてから、階下へおりてきたそうです。
お姉さんの美濃部美津子さんの本に、そんなことが書いてありました。
芸というのは本当に怖いですね。
終わりのない一生の戦いなのです。
今日はここまで、じゃあね。ばいばい。





