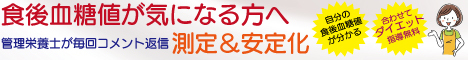街の深み
みなさん、こんにちは。
ブロガーのすい喬です。
街にはやはり深みがなければ面白くないですね。
華やかな表通りも確かに必要だけど。
それと同じくらい、あるいはそれ以上に裏通りが必要なんです。
この両者が適度なバランスで構成されていなければ、街はその力を持ち得ません。
人は華やかな通りを好んで歩きます。
そこには立派なショーウィンドウがあり、装飾もみごとなものです。
銀座や青山などを歩いていると、お店を見ているだけで楽しくなります。
若いカップルがそこを歩いているだけで、絵になります。
しかし時に疲れ果て、明るいところだけには行きたくないと思うこともあります。
そうした心理をうまく操る場所が装置としての裏通りです。

できれば道はくねくねと曲がり、小路で構成されている方がいい。
どこの誰であるのかという個人の名前を消し、無名になれる場所。
そこではもうどこの誰でもない。
1人の弱い人間です。
繁華街と呼ばれる街は必ず、この両面を持っています。
日本中どこへいっても似たような店が増えたとはいうものの、かつての闇市のあとを彷彿とさせるような場所が今でも残っています。
下北沢は消えてしまいました。
今では新宿か、上野のアメ横か、吉祥寺か、かなり整備されてしまったものの浅草にもその匂いがあります。
そこへいくとなぜか人は安心感でるのです。
アジアのマーケットを歩いているような気持になれるからかもしれません。
裏通りは必要
時にはいかがわしい飲屋街になっているところもあります。
それでも裏通りは必要です。
ヨーロッパを旅しても、アジアを旅しても、このことは古今東西同じことのようです。
かつて金沢を旅した時、そうした裏通りがつい目と鼻の先にあるのを見ました。
それは札幌も同じです。
あるいは仙台も青森も、どこへいっても人間のいるところには欲望が渦巻きます。
しかしそうしたことも全て含んで、やはり成熟するためには、深みがなければならないと思います。
人工的に作られたいわゆるニュータウンと称する場所のなんと白々としたことか。
どんなにイルミネーションで通りを飾ってみても、街の深みはありません。
つまりそこには祭りもないのです。
祭りはつねにそうした猥雑な装置として存在してきました。
御旅所の周囲、神社、寺の周囲は精進落としの場所となり、遊郭が発生したのです。

伊勢神宮の周囲のあの賑やかさも独特のものです。
つまり周縁としてのそうした場所を含んで、街は成り立ちます。
下町を散策しようとする人々の中に、憧れをこめた成熟への志向をみてとるのは容易です。
裏通りばかりを好んで撮った写真家が何人もいました。
その反対に表通りの華やかなイルミネーションの世界を撮り続けた人もいます。
どっちも本当です。
嘘じゃない。
上水があれば下水もある。
それが人の世です。
だからこそ、面白いんです。
今日はここまで。
じゃあね。
バイバイ。