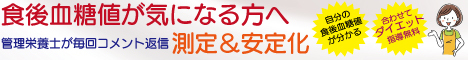幻の大玉牛
みなさん、こんにちは。
ブロガーのすい喬です。
今回は牛丼の話をちょっとさせてください。
牛丼というものを意識して食べたのは、大学に入ってからです。
今のようにチェーン店もなく、それほどにポピュラーなものではありませんでした。
これはぼくがはじめて牛丼に出会った時の話です。
その店はほんとうにひっそりと大学の門の前にありました。
カウンターが無造作にあるだけの学生街の食堂です。
通称、裏門と呼ばれるその周囲には食堂が軒を並べ、昼時ともなると、多くの学生が次々とあたりの店に吸い込まれていきました。
ぼくがその店に入ったのも全くの偶然です。
それまで牛丼というものがこの世にあることを知らず、まったくそれは唐突に注文されたのです。
なぜあの時、牛丼などを食べたいと思ったのかといえば、それは隣に座っていた一人の学生が、実においしそうに食べていたからです。
値段もきっと手頃だったのでしょう。

その店では牛丼が1番の人気メニューだったようです。
何も知らないぼくはただ「牛丼ください」と言ったみたいです。
しかし店のおばさんはそんなことでぼくを許してはくれませんでした。
「大盛り、中盛り、普通盛り?」とすぐに訊かれました。
その他にもいくつかのバリエーションがあったかもしれません。
「卵はどうします?」という問いかけもすぐに後から追いかけてきました。
そこでおなかがすいていたぼくは大盛りで、卵もつけてくださいとおずおず言ったような記憶があります。
というのもとにかく昔のことで、記憶がはなはだアイマイなのです。
すると、店のおばさんは突然「大玉牛一丁!」と叫びました。
おおたまぎゅうという響き
この時、「おおたまぎゅう」という名前がぼくの脳みそに刷り込まれました。
なぜあんなに感動したのか。
今となってはさっぱり思い出せません。
ただ語感がよかったことは確かです。
とにかくいいネーミングだと感嘆しました。
それから数分と待たずにすぐ「大玉牛」はぼくの前に姿をあらわしました。
テーブルの上にのっていた紅ショウガをたっぷりとどんぶりにのせ、後はただ無言でいただきました。
大変おいしかったです。
卵、ご飯、牛肉、タマネギのアンサンブルはみごとなものでした。
味付けもなかなか凝っていました。
もともと牛肉をたべるという習慣は日本にはなかったようです。
牛丼などというものは明治になってからのものです。

福沢諭吉が牛鍋をつついているのを見て、暗殺を考えた人が何人もいるという話があるくらいです。
当時、牛を食べると頭から角が生えると本当に信じられていました。
きっと誰かが、すき焼きのあまりものをご飯にかけたのかもしれません。
その試みにそれほどの時間はかからなかったのではないでしょうか。
これは結構いけるというので、すぐヒット商品の候補になったと想像されます。
ところがそれほどに感動した牛丼にもかかわらず、それから何度も同じ店に行ったという記憶がありません。
あるいは1度で終わったのか、2度目には失望したのか。
そのあたりは定かではありません。
しかしいずれにせよ、あれからあの大玉牛の味に再会していないことだけは確かです。
あれこそ、一期一会と呼べるものなのかもしれませんね。
とにかく若い時代でした。
なにもかもがむしゃらで、なにができるというワケでもないのに、へんに自信だけが身体中にみなぎっていました。
今日はここまで。
じゃあね。
バイバイ。