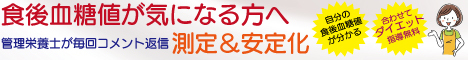本火と本水
みなさん、こんにちは。
ブロガーのすい喬です。
芝居の世界では、舞台上で本物の水と本物の火を使うことを、本火(ほんび)、本水(ほんみず)といいます。
これは一種、畏敬をこめた言葉だね。
人は火や水を怖れるのです。
1番、原初に近い情景です。
野外劇でいったら、薪能ですかね。
何度も見ました。
炎が揺らめいているだけで、心が動きます。
夏の興行などでは涼感をよぶために、水を使うことも多いです。
水の上にステージを作ることもありますね。
この類いの芝居もかなり見ました。
天児牛大(あまがつうしお)が主宰していた山海塾の公演はすごかったです。
全身白塗りと剃髪の舞踏でした。
「水卵」というパフォーマンスでは、彼が水の中に倒れかかるたびに、この世から遠ざかっていくような感傷にひたったものです。
しかし実際の劇場で水や火をつかうことはなかなかに神経のいることです。
殊に地方公共団体などが管理している多目的ホールでは、まず許可していないところの方が圧倒的に多いのです。

ひどくなると、足元の非常灯や、非常口のランプでさえ、一時的にもせよ、消すことは許されません。
かつて見た山崎正和の芝居「世阿弥」にも巧みに本火が取り入れられていました。
能のかがり火と囲炉裏の火をイメージし、2つのシーンで使われていたのです。
どんなにものすごいレベルのライトを駆使しても、自然の火には勝てません。
おそらくその背景には火の本来もっている原始の力があるからでしょうね。
人は火をみると、太古にも原始にも戻ることができる。
最近はやりの焚火のYoutubeも起源はそれです。
薪能の灯りもまさに、揺らめく中での幻想を作り出すのに大きな作用を及ぼしているといえます。
いいですよ。
ゾクゾクしてきます。
曽根崎心中
ぼくにとって一番思い出深いのは演出家、鐘下辰男がひきいる劇団「ガジラ」の公演です。
「曽根崎心中」でした。
もう誰も覚えていないに違いありません。
すごい話ですからね。
こんなにひどい人間がいるのかという典型のような話です。
どうしたって死ななくちゃならない。
もう生きる気力がどこにも残っていないという話です。
最後に平野屋徳兵衛が天満屋お初の首をしめるシーンで、突然、霧のような雨が降ってきました。
きれいだった。
照明の効果がこれ以上はないくらい際立っていました。
千葉哲也の演技は当時から光っていたんです。
彼は今、演出家として活躍しています。

今日の活躍が約束されていたといえます。
その水の美しかったこと。
今でもこの時のシーンは忘れられません。
照明が水に反射して、役者の身体を濡らしていく時間が実に幻想的だった。
しかし本水は使い方が本当に難しいのです。
ひとたび失敗したら、ただの仕掛けに終わってしまう。
歌舞伎では同じ近松門左衛門の「女殺油地獄」で実際に油を使ったという話を聞いたこともあります。
いずれにしても、本物を使うという決断にはそれなりの必然性が必要です。
演出家はぎりぎりまで、自分の感性とのせめぎ合いを余儀なくされるのだよ。
今日はとんでもない話を書きました。
それじゃあね。
バイバイ。