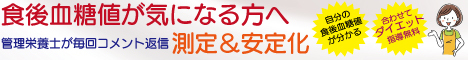志ん朝の高座
みなさん、こんにちは。
ブロガーのすい喬です。
演芸評論家、京須偕充氏の書いた『志ん朝の高座』を読んで、どうしてこういう死に方をしたのかとまた考えてしまいました。
平成13年というから、もう随分も前のことです。
早くから名人などと呼ばれ、ますます寡黙になってしまいましたね。
芸はどこまでいっても完成しないということを1番よく知っていた人です。
この本にはあふれるほどの志ん朝の写真が載っています。
写真集と言ってもいいくらいだね。
三百人劇場での高座の様子がみごとに再現されています。
「首提灯」という演目は音で示しきれないところが多いため、CDにはなっていません。
それも連続写真とともに再現されている。
志ん生にならなくてよかったです。

今はそう思う。
もっと生きていて欲しかった。
この人の華のある芸をもっとみたかった。
落語は消えてしまうからいいのだと美濃部強次はいつもそういっていたといいます。
もちろん、これは彼の本名。
現在活躍している多くの落語家がどれほどの人気を得ようと、志ん朝を抜くことはできません。
それだけ江戸前の気っ風のよさといさぎよさ、華やかさをもってました。
本当に彼の早逝がくやしくて仕方がないです。
音源
あっちこっちにあったのをみんなMP3にしてもってます。
よく聞きます。
しかしやっぱり高座でもっと見たかった。
だんだん調子をあげてきて、顔が紅潮していく時の様子が忘れられないね。
志ん朝があがると、高座がぱっと明るくなった。
ああいう噺家はそう出ないだろうね。
京須さんがある時エレベーターの中で先日の「文七元結」はよかったと褒めたことがあったそうです。
すると、いつものように「だれるよ」ととぼけてふいと横を向く仕草をせず、わずか3秒間ぐらいじっと彼の目を見つめたという。
この話がぼくは大好きです。
志ん朝という人の真骨頂が出ている。
褒めることのない京須さんに絶賛されたことが、よほど嬉しかったんでしょう。
芸がわかる人に心底言われた言葉が五臓に達したのです。
これは高座に上がった人でないとわからない。
自分でもあの高座はよかったと含むところがあったに違いないのです。
実に80分の長尺でありながら、少しもだれ場がなかったといいます。
文七の80分なんてね。

すごい落語だよ。
芸は一代のものです。
だからなおさらくやしい。
もったたくさん聞いておけばよかった。
噺家になるのはイヤだといいながら、気がついたらいつの間にか高座にあがっていたんです。
そういう血が大切です。
そうでなきゃ、名人にはなれない。
芸というのは実にはかないものなんだ。
色々書きたいこともあるけど、今日はここまで。
じゃあね。