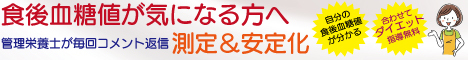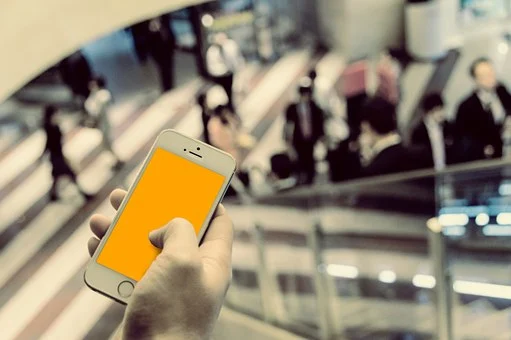香港フラワー
みなさん、こんにちは。
ブロガーのすい喬です。
今朝、突然この言葉を思い出しました。
子供の頃は当たり前のように使っていた単語です。
今でも通用するのでしょうか。
なぜ香港という名前がついたのか。
ちょっと調べてみました。
主に中国の汕頭(スワトウ)や香港地方から多量に輸入され,主として店頭装飾用に用いられているそうです。
現在もこの単語は生きているんですね。
とくにプラスチック製のものが多いようです。
その気になって大きなホームセンターの花売り場を探してみると、ありました。
以前のものより精巧なつくりです。
値段もそこそこします。
かつては本当に安物でした。
いかにもプラスチックでつくりましたといった体裁のものが多かったのです。
それが今では、ちょっとみると、実物かなとふと思ってしまうような出来栄えです。

植物のさまざまな部分が,個々に鋳造されているのがよくわかります。
それぞれパーツが組み合わされて、造花,人造植物,人造果物が大量生産されています。
最近では冷暖房が整っているせいか、生花を保持するのが大変みたいですね。
すぐにダメになってしまうようです。
特に高価なランなどの花は、プラスチック製でも遜色がありません。
正確にいうと、ポリプロピレンなど、さまざまな材質を組み合わせて作っているようです。
あまり費用をかけずに、1年中、同じ品質を保つという意味では無視できないもののようです。
観葉植物も
香港フラワーというと、それこそ、花をイメージするケースが多いようです。
しかし最近は観葉植物もこのタイプのものが多いとか。
丈の高い立派な植物まで、いわゆる香港フラワーだときくと、自分の目がいかにいい加減かよくわかるというものです。
しかしそれだからこそ、ここで言いたいですね。
植物は枯れるからこそ、価値があるのではないでしょうか。
どうしてそんなことを考えたのか。
実は今日、桜の花びらが散るのを目の前で見たからです。
あっという間ですね。
満開になってまだ数日です。
それなのに早くも風に舞って散り始めていく。
この速さはなんなんでしよう。
散華などいう言葉を聞くまでもなく、あまりにもはかないです。

しかしだからこそ、価値がある。
そこに自分の生を重ねてみるというのが、人間なのではないでしょうか。
花があるという言い方をしますね。
能では花を持つということが最も美しいと表現されます。
どうしたら花が持ってるのか。
それを隠せとも言われます。
全てをあらわしてしまったら、そこから珍しさが消えていきます。
それはもう美ではないのです。
秘すれば花とはよく言ったものですね。
だからこそ、まことの花を手にいれるまで、人は戦い続けるのです。
時分の花
若い時の美しさはやがて消えていきます。
本当の戦いはそこからなのです。
これが香港フラワーのように衰えることのない人間なら、美への衝動は生まれないでしょう。

人の世ははかないものです。
あっという間に時が過ぎていくのです。
それでもまことの花をさがす。
だからこそ、愛おしいですね。
若葉の頃
桜の花が散ると、青葉が一斉に出てきます。
その時の美しさも見事ですね。
だからこそ、生きる勇気もでてくるのです。
これがずっと同じ花が咲き続けていたらどうなるのか。
うっとおしいだけです。
いつ咲くのかと思い、咲けばもう散ってしまうのかと嘆く。
そして青葉が顔を出せばやはり美しいと思う。

その繰り返しが生きているということなのです。
人も滅びていく。
だからこそ、愛おしい。
そういうものとして、桜の花びらが散っていくのを眺めていました。
またすぐに次の季節がやってきます。
今度はツツジでしょうかね。
漢字では躑躅と書きます。
髑髏に似ていると思いませんか。
じゃあね。また。