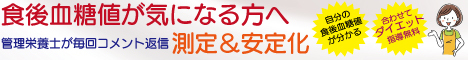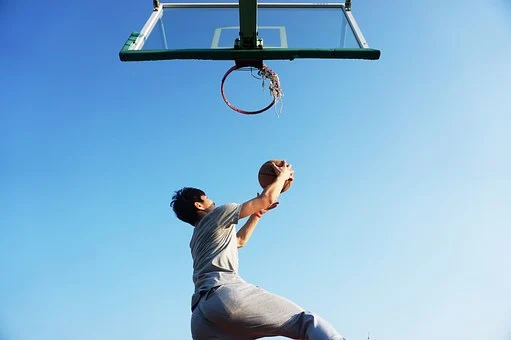話芸の未来
みなさん、こんにちは。
ブロガーのすい喬です。
アマチュアで落語もやってます
ここ数年のコロナ禍にはまいりましたね。
以前なら、毎月あった高座がめっきりと減りました。
今年は1月にやっただけで、この後は4月に予定されているだけです。
その先は夏ごろまでにあるのかどうか。
芸人殺すにゃ刃物はいらぬあくび1つで即死する
これは昔からよく言われています。
今なら、刃物のかわりがコロナですかね。
芸人たちはみんな苦労してますよ。
なにしろ集まっちゃいけないんですから。
ミュージカル「ラマンチャの男」も結局休演になったらしいです。

松本白鷗最後の公演だったらしいですけどね。
コロナには勝てません。
話芸といえば、義太夫、講談、浪曲、落語、さらには香具師のたんか売といったように、さまざまなものがあります。
しかし今日、風俗の変化や価値観の多様化により、それらが生き残るのは並大抵のことではないようです。
少し以前にはテレビでも随分寄席中継もありました。
今では「笑点」を残すのみです。
桂宮治が三平の後に入って、少し視聴率が上がったとさかんにニュースでは言ってます。
逆にいえば、それくらいしかネタがない。
円楽が病気で引っ込んで、そのかわりをどうするのか。
これも手間のかかる話です。
スタッフの気苦労が推察されるというものです。
伯山の人気と落語のリズム
神田伯山の人気はスゴイみたいですね。
彼が出る時の寄席はいつも満員らしいです。
松之丞の頃から人気はありました。
しかし伯山になってから火がつきましたね。
講談が生き残るためには彼の頑張りが必要でしょう。
なんといっても芸人には花が必要です。

出てくるだけで高座が明るくなる。
これが1番大切なんです。
その意味で女性の講談師が多いのも頷けます。
ところが伯山に人気が集まる。
不思議なことばかりです。
たまにBS放送で、落語などをやっているのをみると、なんとも長閑な印象を持ちます。
長屋の噺も貧乏の噺も今では、あまりにも遠い物語になってしまったのかもしれません。
「百川」のように地方人を軽く扱った噺は江戸っ子にはうけるでしょう。
また「芝浜」や「子別れ」のような噺。
あるいは遊郭を舞台にした作品。
若旦那を扱ったものなどは確実に残ると思います。
「明烏」の持つ上品な色気や、「船徳」のとぼけた味はやはり捨てがたいです。
現代落語論
落語家の中でも特に、亡くなった立川談志は今の時代にどのように落語が受け入れられるのか、1人で苦しんでいたようです。
彼の『現代落語論』を読むと、いかにこの芸を愛しているのかが、よく理解できます。
それは本当に息苦しいほどです。
面白いと言われる落語ですら、このような状況なのです。
ましてや義理、人情が主体の講談、浪曲となると、若い人にはもうアピールしないのかもしれません。
伯山の人気はどこからきているのか。
それをもう少し考えなくてはいけません。
こういう言い方は厳しいですが、時代と共に衰退を余儀なくされていく側面がないワケではありません。

義理人情の渡世ものだけでは浪曲も無理です。
玉川大福が浪曲で気を吐いている分野はどこか。
やくざがでてくる話ではありません。
隣の人のお弁当の中身をテーマにしたり、銭湯の違いをネタにしたものです。
人気が出てきたとはいうものの、ここからが苦しいでしょうね。
それはかつてのたんか売の衰退と同じです。
小沢昭一さんが苦労して集めた多くの話芸のテープを聞いていると、とても懐かしいのですが、やはり古さを感じます。
バナナのたたき売りや、山伏や行者の恰好をしてものを売る話芸など確かに絶品です。
しかし残念ながら今の時代にはあいません。
客層の変化
原因の一つとして、話芸にじっと耳を傾ける良質の客がいなくなったことも、あげられるかもしれません。
昔は噺の巧拙を瞬時に判断し、どんなに面白くてもにこりともしない常連の客の前で、噺家は鍛えられました。
どの寄席にもこういう「通」と呼ばれる人がいたのです。
彼らは芸にはとても厳しい反面、落語家をあたたかく育て上げました。

結城昌治の『志ん生一代』を読んでいると、そうした時代のぬくもりを感じます。
酒を飲んで高座にあがり寝込んでしまう噺家を、観客は許しました。
それは彼の芸が一流だった故のことでした。
志ん生の噺の間は独特なものです。
さてこれからどうなるのでしょうか。
今日はここまで。
じゃあ、またね。