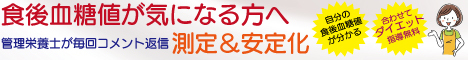マニュアル
みなさん、こんにちは。
ブロガーのすい喬です。
マニュアルは本当に便利です。
新人を教育する時には、この通りやればとりあえず形になります。
しかしそれで終わりということになってしまうと、実に索漠たる気持ちになりますね。
これはある落語家がよく噺のまくらで使うマニュアルばかのネタです。
その師匠がある日、楽屋にいる若い前座さんのために、とあるハンバーガーショップに立ち寄ったと思ってください。
そこで彼は10個ばかり注文しました。
いつものようにその店員さんはありがとうございます、とはきはきした声で挨拶をしました。
そこまではいいのです。
その次の台詞が「こちらでお召し上がりになりますか」というものだったとか。

まさか10個のハンバーガーをたった1人で食べるワケがないじゃないかと彼は高座で吠えておりました。
さらに、コーヒーを注文すると、こちらコーヒーになりますと呟いたとか。
またまた彼はかちんときて、コーヒーになるということは、その前はなにか別のものだったのかとつい訊きたくなったそうです。
1つ1つの言葉を大切にしている落語家だからこそ、気づく様々な表現のおかしさということなのでしょうか。
ごゆっくりどうぞ
昨日もとある店に入り、コーヒーとパンを注文したら、ごゆっくりどうぞと挨拶されました。
このお店は入り口にさまざまなパンを置いて、お客が勝手にトレイにのせてとる方式になっています。
そこまではいいのです。
しかし、いちいちパンが焼けるたびに、その商品についての解説をし、あたたかいうちにどうぞというようなことを店員が一斉に呟きます。
時には誰かのいうことを復唱したりもします。
マニュアルがあるらしいということは、しばらく店の中にいれば、誰でも気づくのです。
毎回、同じことを言うので、なんとも不思議な光景に見えて仕方がありません。
自分で全てを誰にも言われる前に気づき、行動するということは大変な努力を要します。
それを短時間でこなすためにマニュアルが必要となるのでしょう。
しかし真のサービスは、その彼方にあるということもまた事実なのです。

何かを注文するたびに、「よろこんで」と叫ぶ居酒屋チェーンもあります。
ドアを開けると「ようこそ」と挨拶するファミリー・レストランもまた異様な風景です。
お客が正面玄関に現れるたびに、ごく自然に応対するドアマンの話をテレビでみたことがあります。
時にはそのお客の名前を口に出して迎えるそうです。
常連のお客様の顔と名前はみんな覚えているとか。
ここまでくると神技ですね。
仕事のレベルをはるかに超えてます。
部屋に残していったたった一枚のメモでも、必ず捨てずに保管しておくというある老舗ホテルの話を読んだこともあります。
その1枚のメモ用紙が、お客様にとってどれほど大切で意味があるものなのかまで、想像した末の行動だとか。
たかがマニュアル、されどマニュアルなのかもしれません。
前座
落語をやっていると、プロの噺家さんと落語会のあとで打ち上げと称してちょっとお酒を飲む機会もあります。
そういう時に師匠は前座を一緒に席に着かせます。
しかし彼らはすぐにお酒を飲もうとはしません。
完全なタテ社会です。

師匠が少し頂戴しなさいと声をかけてくれるまでは飲んだり食べたりしてはならないのです。
さらに同席したお相手のコップにお酒がなくなると、注文をしたり、ついだりと誠に忙しいのです。
たえずテーブル全体に目配りをしなければなりません。
その気の使い方はとてもマニュアルなどで管理できるようなものではありません。
何が起こるかわからないのです。
理不尽
時にはとんでもなく理不尽なことが起こることもあります。
それをさっと目の前でになかったことにしていく目端のききかたが、芸の肥やしだとよく言われます。
落語は人間の話です。
人間はけっしてマニュアル通りの動きはしません。
まさかというようなことを平気でするのです。
立川談志はよく弟子に無茶ぶりをして、その処理能力を計っていたそうです。
それでも顔色に出さず、その場を切り抜ける才覚がないと、芸は伸びないといいます。
誰よりも先にたって、そして目立たない。
これが1番大切なのです。
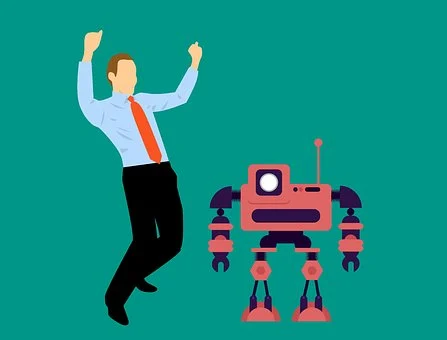
あの前座はよく働く。
気がきくといわれれば、巡業先に連れていってもらうことも増えます。
師匠の身のまわりのことをしているうちに芸の本質を知るのです。
けっしてマニュアル通りにはいきません。
そこに人間相手の商売の難しさがあるんでしょうね。
誰も学校では教えてくれないのです。
だからこその修行期間なんでしょう。
今日はここまでね。
See You Again。