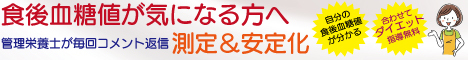中国人との付き合い方
みなさん、こんにちは。
ブロガーのすい喬です。
作家の邱永漢が亡くなってかなりの月日が経ちました。
稀有な人物でしたね。
日本と台湾を通じて名前を知られた実業家です。
「金儲けの神様」と呼ばれました。
亡くなってもう10年です。
1955年に小説『香港』で第34回直木賞を受賞しました、
外国人としては最初の直木賞受賞者です。
全てが異色だといっていいでしょうね。
日本では文学を志す人は清貧に甘んじるというのが普通でした。
それなのに彼は、株で儲けるのもうまかったのです。
数年にわたって邱永漢の本をかなり読んだ時期がありました。

妙な経済評論家の本より説得力があったからです。
全てを経済の面からみていくために、政治の話にも実感がありました。
著書の中でもユニークなのは日本人論です。
もちろん、中国人と対比して書いています。
『騙してもまだまだ騙せる日本人―君は中国人を知らなさすぎる』などというタイトルを見ただけで驚きますね。
なんとも物騒なタイトルです。
この題は上海で仕事をしていた日本人商社マン達の川柳大会で特選をとった作品からとったものであるといいます。
どこかほろ苦い味のする川柳です。
これが実感なんでしょうね。
ぼくも2回ほど中国には行っています。
ある日本企業の現地スタッフに話を聞いたことがありました。
その苦労話にかなり似ているなというのが、正直な感想です。
それほどに外れた突飛なものではないのです。
商売の流儀
政治の世界の話はどうもきな臭いですね。
尖閣列島の話題やアジア地域での海洋開発などの話になると、中国という国の本音が見えなくなります。
しかしその話はおいておいて、今回は商売の面からみていこうという話です。
これほど日本人と考え方が違うのかということが、この本を読んでいるとしみじみわかりますね。
この差を簡単に埋めて、理解し合うことは難しいと感じます。
いちはやく世界標準の考え方をビジネスの世界に取り入れた日本と、まだまだ個人と個人の関係で商売をしているお隣の国、中国とは何もかもが違います。
邱永漢はそのあたりを表と裏から自在に見てとっています。
読んでいて最後まで飽きません。
とにかくものを売ったら後はお金が入ってくるだろうと考えるのがごく普通の日本人です。
どうもその常識は通用しないようです。

売掛金を踏み倒されるのは日常茶飯事だと聞きます。
中国人は政府を信用せず、愛国主義という考え方もほとんどないという内容にも驚きます。
拝金主義は大阪の商人に似たところがあるといいます。
全ての労働は自分の家族のためというのが彼らの考え方の基本です。
ちょっとした会社でも黙っていると、あっという間に一族が次々と就職してしまうらしいのです。
じっと我慢して利潤をあげるまでいい商品をつくるというよりは、てっとり早く、少々粗悪なものでも儲けをあげてしまいます。
少ない賃金で我慢することなどは絶対にしません。
労働者の気質
日本の会社もかなり中国に進出しています。
しかし現場で働いている人たちの気質はまるで違います。
少しでも賃金が高ければ、すぐに別の会社に行ってしまい、長くとどまることはないそうです。
元々、日本企業はいい給料をだしていました。
しかしそんなことにはすぐ馴れてしまうのでしょう。

彼らはさらに高いところをめざし、最終的には起業を試みます。
人の下でこきつかわれるくらいなら、自分がトップに立ちたいというのが、中国人の生き方なのです。
そういう意味ではアメリカ人と気質が似ているといえますね。
政治の駆け引きでも似た要素を持っています。
ともに食事をすることの大切さ
彼らととにかくきちんと仕事をしたかったら、まず一緒に食事をすることです。
家族同士仲良くならなければ、本当の関係はつくれないといいます。
そこまでして親しくなると、他では得られない権利を与えられたりして、いい商売もできるらしいのです。
とにかく誰かに紹介をしてもらいながら、顔と顔をつなぐのが基本です。
相手の面子をたてていくというのが中国でのビジネスなのです。
田中角栄があれだけ高く評価されているのも、ある意味、彼が日中の関係をつくりあげたということへの感謝があるからでしょう。

「老朋友」と呼ばれるところまでいけば、そこから後は随分楽になるようです。
基本的に人脈をつくるところからしか、中国には入り込めません。
入り口で論理を振りかざしても、痛くも痒くもないのです。
誠に難しい国と交渉をしなくてはなりませんね。
民族性の違いというのは、本気でつきあってみないと見えてこないもののようです。
今日はここまで。
じゃあね。