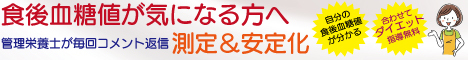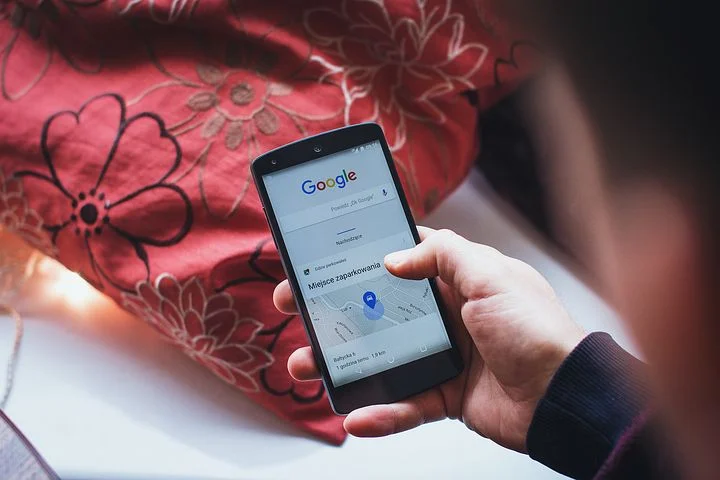江戸前落語
みなさん、こんにちは。
ブロガーのすい喬です。
2001年、古今亭志ん朝が亡くなりました。
あれからもう20年以上の月日が経ちます。
あまりにも早い死でした。
落語家は60才を過ぎてから、芸の実りの時期を迎えます。
63才という年はあまりにも若すぎました。
彼の兄、金原亭馬生もお酒のせいで早くに亡くなってしまいました。
本当に惜しい咄家を次々となくしたものです。
この穴は当分誰にも埋められないと思いました。
そのことを一番よく知っていたのは、全ての噺家達です。

本当に寄席の世界は意気消沈してしまったのです。
彼は父親、古今亭志ん生の芸を幼い頃からずっと見て育ちました。
自然に江戸前落語の第一人者になっていきましたね。
本当は外交官になりたかったようです。
しかし親父がこんなにいい商売はないぞと耳元で囁き続けました。
ドイツ語が好きだったのです。
得意な語学を使って世界を歩く気概でいたのでしょう。
しかし気がつくと、着物を着て高座に出ていました。
気っぷのいい彼の芸に触れたことがありますか。
今でもYoutubeにたくさん動画が残っています。
江戸っ子が目の前にいるようですね。
気品
口跡がみごとでしたね。
いつも清潔で、芸に気品がありました。
志ん朝はいずれ父の名跡を継ぐべき咄家だったのです。
本人はまだまだと言っていましたが、周囲の誰もがいずれは大看板を背負い、日本の話芸の粋を生きて体現する人だと思っていました。
ぼくももっと高座をたくさん見ておけばよかったと思います。
最後に聞いたのは亡くなる数年前、井の頭公園近くの公会堂ででした。
ていねいな枕から次第に本題に入っていくにつれ、昂揚していきます。
人物の造形が確かですから、話の展開に訳もなく入っていってしまうのです。
父親譲りの「火焔太鼓」も好きでしたが、もっとのんびりとした「船徳」などの若旦那ものがよかったです。
「百川」「錦の袈裟」といったとぼけた噺も好きでした。
残された記録だけでしか話を聞けないのが本当に悔しいです。
もちろん本格的な長い噺もいいですね。

「品川心中」「文七元結」「愛宕山」。
どれも素晴らしいです。
あの独特の表情、スピード感が忘れられません。
かつて落語協会に内紛がありました。
立川談志が暗躍したとのことです。
その結果、三遊亭圓生が自分の弟子を連れ、会を脱退しました。
この騒動の時、「こんなことをしている場合じゃありません」と言って、落語界全体の団結を訴えていたのが今さらのように思い出されます。
志ん朝の穴を誰が埋めていくのかと考えると、やはり柳家小三治しかいませんでした。
事実、志ん朝の病気休演の舞台を支えたのは小三治です。
しかし芸風は全く違います。
談志も噺はうまいですが、品格にかけるところがあります。
客の好悪が激しかったですね。
小三治の噺はどこかとぼけていて、ついクスリと笑わされてしまいます。
小三治の死
その小三治も鬼籍に入りました。
いずれ小さんの後を継ぐと思っていましたが、名前は小三治のままでしたね。
それでも志ん朝の抜けた穴は大きくて深いです。
あれだけ毒舌で知られた談志が金を払ってでも噺を聞きたいのは志ん朝だけだと言っていました。

全くその通りだと思います。
大看板たちが次々と亡くなり、次に名人と呼べる人は誰なのでしょうか。
芸は一代限りのものです。
亡くなれば、そこで消えます。
落語界の明日
今や落語家1000人の時代です。
とんでもない数の噺家がいます。
その中で本当に江戸の風を吹かせることのできる人は何人いるのか。
これからの時間の堆積に耐えられる人は誰なのか。
考えてみるだけで楽しいです。

柳家一門か、春風亭か、入船亭か、桂か、あるいは古今亭一門か。
三遊亭円丈がなくなり、新作派の人垣にも動きがあります。
次々と真打も誕生しています。
その中からいずれ次の世代を担う噺家が出るに違いありません。
江戸前の粋な芸風をみせてほしいと心から思いますね。
今日はここまでにしておきましょう。
じゃあまたね。