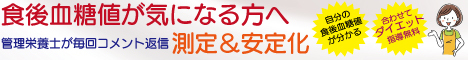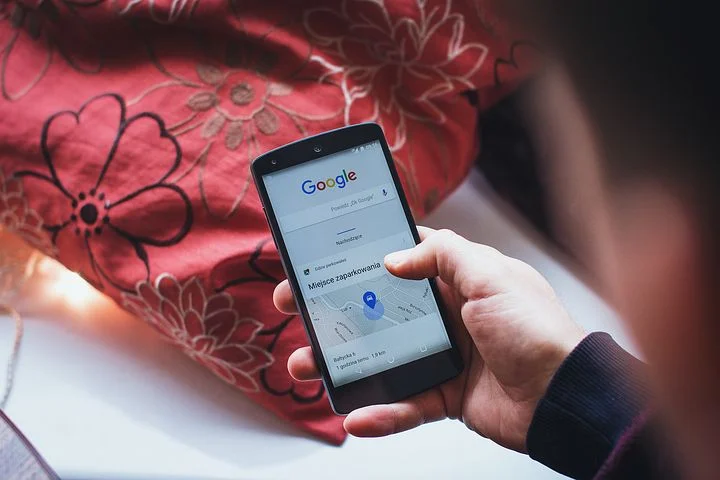おつかれさま
みなさん、こんにちは。
ブロガーのすい喬です。
鳥飼玖美子さんの本『通訳者たちの見た戦後史』を読んでいたらこんな記述がありました。
御存知ですよね。
同時通訳で英語教育の権威として知られています。
なんの話かわかりますか。
挨拶によく使われる「おつかれさま」という言葉が気になるというのです。
外国人から「オツカレサマ」ってなんのことですかとよく訊かれるらしいんですね。
「あなたはつかれているに違いない」と訳すと、なんのことかよくわかりません。
You must be tired. が直訳に近いですね。
しかしなぜあなたからそんなことを言われなくちゃならないのかといってまた聞き返してくるそうです。
そんなにくたびれちゃいないというアピールなのかな。
最近はなんでも「おつかれ」ですからね。

この表現は元々はテレビの業界から出た言葉らしいです。
収録を終えた後、声をかけあってスタジオを出る時の表現のようです。
それをタレントが番組で使い、日本中に広がったとか。
おつかれさまの便利なところは目上も目下も関係なく、どちらからでも使えるのです。
最近では「お疲れ様」から始まるメールもよくみかけます。
なんかへんな感じがしますけどね。
相手が自分より偉いと70%が「おつかれさま」を使うそうです。
さらに相手がじぶんより目下でも53%が「おつかれさま」、36%の「ごくろうさま」よりは多いみたいです。
今はどこでも
よくよく気にしていると、確かにおつかれさまは多いですね。
学生と教師のあいだではどうなのか。
彼女はよく学生におつかれさまでしたと声をかけられたそうです。
教えるのが商売なんだから、関係ないと叫ぶのも大人げないと感じたのでしょう。
最近はとくになにも言わずに微笑み返すそうです。
なるほどそんなものかもしれません。
さすがにメールがおつかれさまで始まっていると、まだ疲れていませんから大丈夫と返事をしていたそうです。
しかしそれもやめたとか。
多勢に無勢というやつですね。
日本語の使い方としてはどんなもんでしょうか。
あんまりこなれてはいないような気もします。
いずれ、なんでもおつかれさまで済ますということになるんでしょう。
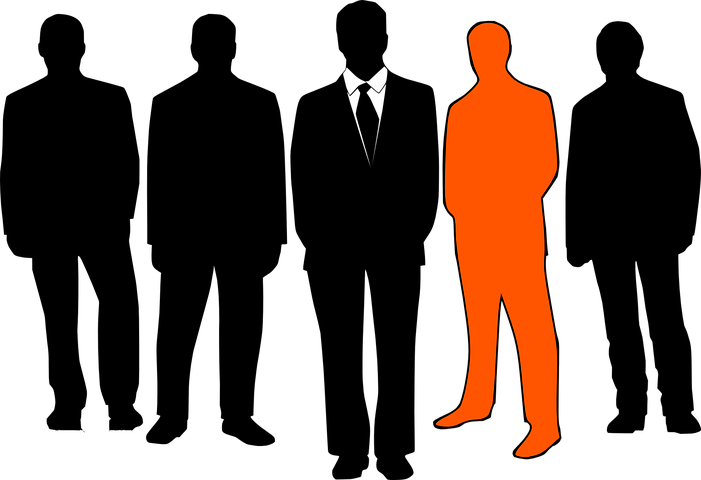
確かに便利ではあるけれど、英語に直訳したのではダメ。
そこで最近ではなんと訳すのか。
ちょっと調べてみました。
それによれば、ねぎらいの意味では次の3つです。
Good job! / Well done!
よくやった!
Thank you for your hard work today.
今日は一生懸命働いてくれてありがとう。
You did an excellent job!
素晴らしい仕事をしたね!
メールでのおつかれさまはどうでしょうか。
I hope you are well.
お元気にされていることと思います。
I hope this email finds you well.
お変わりなくお過ごしのことと思います。
こんなところです。
疲れているに違いない
間違っても直訳だけはしないことです。
そんなことはわからないですからね。

しまいには余計なお世話だと叱られそうです。
通訳というのは本当にハードな仕事です。
特に政治や、経済に絡む交渉事の時は微妙なニュアンスを正確に伝えなければなりません。
善処します
難しいのは日本人同士が使う政治用語を訳す時ですね。
よく聞くのが「前向きに善処します」という表現です。
これはYesなのかNoなのか。
あなたはどちらだと思いますか。
同じようなのに「考えておきます」というのもあります。
これも謎ですね。
外国人は考えておくといったから、考えたんだろうとしばらく後に訊ねます。

すると日本人は完全にその事実を忘れているのです。
つまりこれはNoのサインなのです。
善処しますは英語でなんというのか。
通訳はその時の内容によって微妙に使い分けます。
単純に訳せばこうです。
I will do my best.
もっと政治的に訳すと次のような表現が考えられます。
I will do what I can.
ニュアンスが全く違いますね。
これくらい言葉というものは厄介なんです。
今日はここまで。
See You Again。