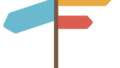岩鼻や
みなさん、こんにちは。
元都立高校国語科教師、すい喬です。
今回は芭蕉十哲の1人、向井去来について考えてみます。
松尾芭蕉の信望も大変厚かった人です。
落柿舎(らくししゃ)という草庵が京都市嵯峨野にありますね。
向井去来の別荘として使用されていた場所です。
命名の由来は、庵の周囲の柿が一夜にしてすべて落ちたことによるものだとか。
芭蕉も3度ほど訪れ滞在をしました。
『嵯峨日記』を著した場所としてもよく知られています。

その向井去来が、自分の句を芭蕉に見てもらった時の話が、今日の主題です。
登場人物は松尾芭蕉、作者本人、向井去来、門人の濱田洒堂(はまだしゃどう)の3人です。
洒堂の名前はあまり聞いたことがないかもしれません。
江戸時代前期から中期にかけての俳人です。
去来の俳句に、どのような解釈がなされたのか。
師、芭蕉の理解ははるかに作者、去来の思惑を超えるものでした。
わずか17文字の中に世界をどう築き上げるのかというテーマは、想像以上に深いものがあります。
内容をじっくりと検討してみましょう。
本文
岩鼻やここにも一人月の客 去来
先師上洛のとき、去来いはく、「酒堂(しゃどう)はこの句を、『月の猿』と申し侍れど、予は、『客』まさりなん、と申す。いかが侍るや。」
先師いはく、「猿とは何事ぞ。汝、この句をいかに思ひて作せるや。」
去来いはく、「明月に乗じ山野吟歩し侍るに、岩頭また一人の騒客を見つけたる。」と申す。
先師いはく、「ここにも一人の月の客と、己と名乗り出づらんこそ、いくばくの風流ならん。

ただ自称の句となすべし。この句は我も珍重して、『笈の小文』に書き入れける。」となん。
予が趣向は、なほ二、三等もくだり侍りなん。
先師の意を以て見れば、少し狂者の感もあるにや。
退いて考ふるに、自称の句となして見れば、狂者の様も浮かみて、初めの句の趣向にまされること十倍せり。
まことに作者その心を知らざりけり。
【注】
先師 先生(ここでは松尾芭蕉のこと)
騒客 風流人 文人 詩人
狂者 風流に徹した人 風流人
現代語訳
岩鼻やここにも一人月の客 去来
(明月の夜、月に浮かれて句を考えながら山野を歩いていると、岩頭にも一人、自分と同じく月に心を奪われている風流人がいたことだよ。)
先師(芭蕉)が上京されたとき、私が言いました。
「洒堂(しゃどう)はこの句の下の句を、『月の猿』としたほうがよいと申しましたが、私は、『猿』よりも『客』のほうがいいだろう、と申しました。
先生はどう思われますか。」

先師が言うには、「『猿』とは何事だ。とんでもないことだよ。 おまえはこの句をどう思って作ったのかな。」
私が答えて言うには、「明月に浮かれて、山野を句を吟じながら歩いていましたところ、岩頭にもう一人の風流人を見つけた時の情感を詠みました。」と言いました。
それに対して先師が言うには、
「『ここにも一人の月の客がおりますよ』と、自分から月に向かって名乗り出たほうが、どれほど趣深くなるだろうか。
ただ自分からも名乗り出た句とする方がずっといい。
この句は私も高く評価して、『笈の小文』に書き入れたのだ。」と言われたのです。
俳句の解釈
この話は「岩鼻や」の句についての、作者去来の意図、酒堂(しゃどう)の解釈、芭蕉の解釈の違いを通して、芸術性の高さを論じる話です。
作者去来の意図以上にレベルの高い解釈をした、芭蕉の鑑賞力の卓抜さを読み取ってください。
少し解説をします。
作者は向井去来です。
彼は最初「月の人」というイメージをずっと考えていました。
つまり「岩鼻をのぼって月を見に行くと、そこには一人の人がいた。」という趣向でこの句を作ったそうです。
しかし同じ芭蕉門人の濱田酒堂は「月の客」ではなくて「月の猿」として方が面白いのではないか、とアドバイスしたのです。
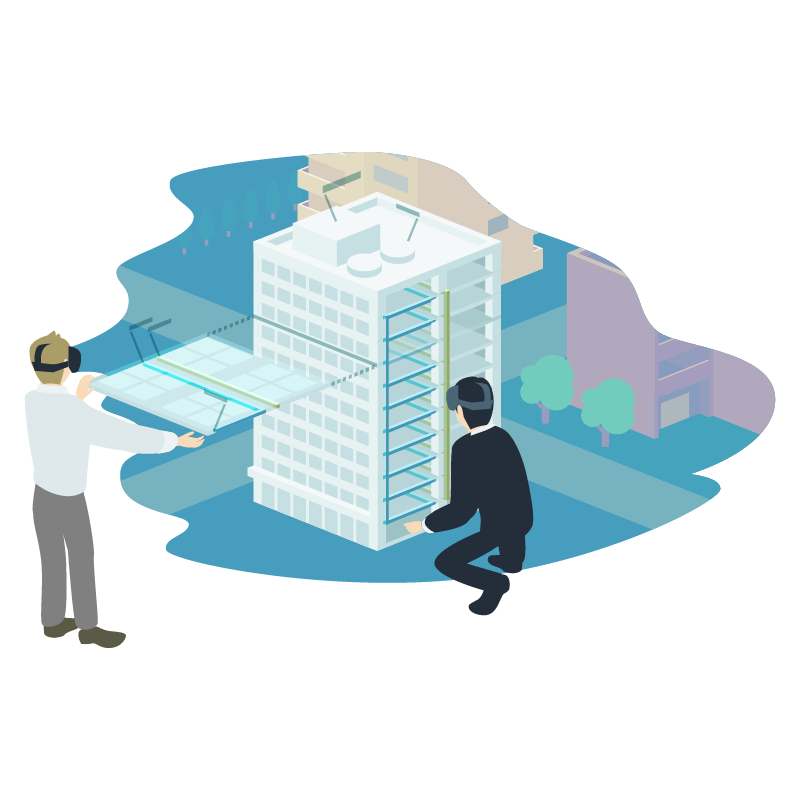
そこで自信を失った去来は芭蕉に問いました。
師匠である松尾芭蕉は、酒堂の意見に反対しました。
「岩鼻よ、ここに私が月の客としているぞ」という意味の方がよいと言ったのです。
去来は自分以外の人間をもう一人想像しました。
しかし芭蕉はそこに立っているのが、去来自身である方が、より力強いと判断したのです。
去来の句は、「岩の突端にも一人、自分と同じように月見をする人がいる」という意図で作った句でした。
ところが芭蕉はこの句を目にしたときに「月よ、ここにも私のような風流人が一人おりますよと、自分から名のり出た句」だと解釈したのです。
構図の違い
意味がわかりますか。
自分以外の人間がそこに立っている姿と、私だけがそこに立っているという構図の違いです。
去来は芭蕉の意見を聞き、やはり先生はすごいと唸ったのです。
芭蕉は他人でも猿でもない、たった一人の風狂の自分が、そこで月の光を浴びている図を作り出しました。
自分から名乗り出るという仕掛けです。
作者自身、自分の句の本当の意味を知らなかったと反省したのです。
もちろん、17文字の文芸ですから、どのようにでも解釈できます。
自分以外の他者がそこにいてもかまわないのです。
しかしそこに名乗り出た去来自身の姿を投影させた時、岩頭に立つ、一人の俳人の姿が見えたのでしょう。

芭蕉がなぜこの俳句を『笈の小文』に書き入れたのかといえば、一人の月の客という俳人の姿が、趣深くみえたからでしょう。
月の客と自分を言い切ってしまえば、そこに滲み出てくるのは「風狂」の姿です。
他人ではなく、他ならぬ自分を突き放して提出した潔さとでもいえるでしょうか。
私の趣向は、師の考えに比べればさらに二、三段も劣っているだろう。先師の考えで見れば、少し風狂の人の感もあるのだろうか。
ここまでを簡単にまとめます。
①去来の考え
「名月を眺めようと岩鼻にいくと、なんとそこにはすでに風流をたしなむ人がたたずんでいた」
②芭蕉の考え
一人の風狂の人が月に向かって「ここにおまえの客がいるよ」と自身で呼びかけている。
それが去来その人だという構成です。
猿は論外としても「客」を他者ではなく、自分に仮託したことで別の世界観を構築したのです。
俳句の世界は文字数が少ないだけに、読み取る人間の懐の深さが試されます。
芸術的センスです。
スポンサーリンク
いい話なので、ここに紹介しました。
今回も最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。