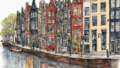現代の国語
みなさん、こんにちは。
元都立高校国語科教師、すい喬です。
今回は教科書の話をします。
2022年度から高校国語の教科書が大幅に改訂されました。
新学習指導要領における「国語」は、現代の国語・言語文化・論理国語・文学国語・国語表現・古典探究の6科目から構成されています。
特に話題になったのが「論理国語」と「文学国語」に大きく分割されたことでした。
多くの学校が4単位の「文学国語」を捨てて、「論理国語」に傾いていくのではないかと危惧したのです。
近年の大学入試共通テストに向けて、論理性や実用性などにまで踏み込んだ内容を過度に重視することに対して、多くの教師が不安を抱きました。
従来なら必ず学ぶはずの定番教材が全て抜け落ちてしまう可能性があったからです。
近年の傾向として、生徒は難解な表現で書かれた小説などあまり読もうとはしません。
それでなくてもツイッターのような短文だけに頼りがちです。
語彙も急速に落ちています。
自分の感情を言葉で表現することのダイナミズムを完全に失いつつあるのです。
「ダサい」「エモい」「エグい」「ヤバい」などに代表される形容詞や「マジ」「チョー」に代表される言葉を連ねれば、今の会話はできます。
その裏に隠された微妙な感情はどこかに捨て去られてしまうのです。
高校生の時代にある程度、普段読むことのない作品に触れることは大きな意味を持ちます。
その意味で文学教材を多く外してしまうことに、違和感がありました。
改訂初年度の心配は必修の「現代の国語」と「言語文化」にあったのです。
従来の「国語総合」がそれぞれ2単位ずつに分かれた結果です。
ポイントは「現代の国語」が論理的な文章、実用的な文章。
「言語文化」が上代(奈良時代ごろ)から近現代にかけての文学的な文章にあったのです。
素直に文科省の指示を受け、「現代の国語」を編纂した教科書会社は文学作品をほとんど載せませんでした。
「現代の国語」は読む教材に、評論文など「現代の社会生活に必要とされる論理的な文章及び実用的な文章」を載せることとするとされていたのです。
文科省の解説には「小説、物語、詩、短歌、俳句などの文学的な文章を除いた文章」という説明がありました。
もう一方の「言語文化」では「古典及び近代以降の文章」とされ、小説や随筆、漢文・古文などを扱うこととされました。
ところが、ここからが騒動でした。
真面目に文学教材をカットした教科書会社が多くあった中で、唯一、5つも小説を載せた教科書が検定で合格したのです。
第一学習社(本社・広島市)がそれです。
掲載された作品は以下の通りです。
芥川龍之介「羅生門」
原田マハ「砂に埋もれたル・コルビュジエ」
夏目漱石「夢十夜」
村上春樹の「鏡」
志賀直哉の「城の崎にて」
他の会社の教科書は指示通り創作が1つも掲載されていませんした。
この結果、採用シェアが大きく変わり東京書籍版を抑えて、第一学習社が最多となりました。
簡単にいえば、現場の先生は使いやすい教科書に走ったのです。
それ以前の「総合国語」では、最初に必ず「羅生門」が載っていたのです。
急になくなってとまどっていたところ、第一学習社版にだけあったので、飛びついたのが実情でしょう。
なぜ掲載してはいけないという指示があったにも関わらず、あえて載せたのか。
さらになぜ文科省が、教科書として採択したのかについては、今となっても不明です。
何か圧力があったのか、忖度があったのか。
それもわかりません。
結果的には正直ものがバカをみたということになりました。
一部の教育委員会からは文科省にかなり問い合わせがあったようです。
本当に採択してもいいのかということです。
当然でしょうね。
今年の場合
教科書は通常4年ごとに改訂の機会があります。
どこの会社でも大幅な内容の更新が行われます。
数年がたち、いよいよ前回の問題になった「現代の国語」も新しい顔を見せました。
それが今回の大きな話題なのです。
一言でいえば、文科省が小説の掲載をかなり認めたことです。
想定していなかった「現代の国語」で、なぜ増えたのか。
以前のイメージでいえば、「現代の国語」は論説や紹介文、企画書や法令文などを扱うということになっていました。
しかし、今年の3月の段階では収録内容にかなり変化があります。
ポイントは4社6点が定番教材の芥川龍之介の「羅生門」を掲載したことです。
単純に文学教材として載せたのでは検定が通らないことを予測して、変化球にしました。
読解中心ではなく、この教材から報告文を書いたらどうなるかなどと工夫をしたものです。
従来行われてきた、登場人物、下人の心情に対しての理解というよりも、その行動をより俯瞰して捉えたらどのように書けるかということなのです。
その結果、無事に通過しました。
教科書の編纂には多くの人の手がかかっています。
コストも大変なものです。
それが検定不合格などということであれば、なんのための労力だったのかということにもなりかねません。
それだけに文科省の意向を読み解くということが大切なのです。
文学の教材して、下人の心情を汲み取るだけの教材では、新しい国語の理解としては不十分ということなのでしょう。
教員時代を通じて、何度この小説を扱ったかわかりません。
1年生の国語を持った年は必ず数回ずつ講義しました。
ほとんど覚えているといってもいいかもしれません。
試験にどこを出すかも決まっています。
「すればはどこまでもすればであった」などという文脈から、下人の心情はどのように変化をしていくかを読みとるのです。
芥川龍之介は心理描写が巧みで、おもわず引き込まれていきます。
善悪の思想もまだかたまっていない空腹をかかえた若い下人が、羅生門の楼上で繰り広げられる光景をみて、どう変化するか。
それを時系列で追いかけていくワケです。
刻々とかわる心の中をそれこそ、分け入るようにしていきます。
その時の生徒たちの反応は実にさまざまでした。
今日の日本において、このように苛酷な状況を垣間見る機会はありません。
それだけにかれらにとっても新鮮な体験であったのでしょう。
よく授業を聞いてくれました。
高校に入って最初に習う教材としては恰好のものだったと言えます。
文章の喚起力
最初の設定のところを少しみてみましょう。
元々『今昔物語』からとったと言われている作品だけに、時代の雰囲気が言葉の中にもよく出ています。
ある日の暮方の事である。
一人の下人が、羅生門の下で雨やみを待っていた。
広い門の下には、この男のほかに誰もいない。
ただ、所々丹塗の剥げた、大きな円柱に、蟋蟀が一匹とまっている。
羅生門が、朱雀大路にある以上は、この男のほかにも、雨やみをする市女笠や揉烏帽子が、もう二三人はありそうなものである。
それが、この男のほかには誰もいない。
何故かと云うと、この二三年、京都には、地震とか辻風とか火事とか饑饉とか云う災がつづいて起った。
そこで洛中のさびれ方は一通りではない。
旧記によると、仏像や仏具を打砕いて、その丹がついたり、金銀の箔がついたりした木を、路ばたにつみ重ねて、薪の料に売っていたという事である。
洛中がその始末であるから、羅生門の修理などは、元より誰も捨てて顧る者がなかった。
するとその荒れ果てたのをよい事にして、狐狸が棲む。
盗人が棲む。
とうとうしまいには、引取り手のない死人を、この門へ持って来て、棄てて行くと云う習慣さえ出来た。
そこで、日の目が見えなくなると、誰でも気味を悪るがって、この門の近所へは足ぶみをしない事になってしまったのである。
その代りまた鴉がどこからか、たくさん集って来た。
昼間見ると、その鴉が何羽となく輪を描いて、高い鴟尾のまわりを啼きながら、飛びまわっている。
ことに門の上の空が、夕焼けであかくなる時には、それが胡麻をまいたようにはっきり見えた。
鴉は、勿論、門の上にある死人の肉を、啄みに来るのである。
もっとも今日は、刻限が遅いせいか、一羽も見えない。
ただ、所々、崩れかかった、そうしてその崩れ目に長い草のはえた石段の上に、鴉の糞が、点々と白くこびりついているのが見える。
下人は七段ある石段の一番上の段に、洗いざらした紺の襖の尻を据えて、右の頬に出来た、大きな面皰を気にしながら、ぼんやり、雨のふるのを眺めていた。
作者はさっき、「下人が雨やみを待っていた」と書いた。
しかし、下人は雨がやんでも、格別どうしようと云う当てはない。
ふだんなら、勿論、主人の家へ帰るべき筈である。
ところがその主人からは、四五日前に暇を出された。
前にも書いたように、当時京都の町は一通りならず衰微していた。
今この下人が、永年、使われていた主人から、暇を出されたのも、実はこの衰微の小さな余波にほかならない。
だから「下人が雨やみを待っていた」と云うよりも「雨にふりこめられた下人が、行き所がなくて、途方にくれていた」と云う方が、適当である。
下人の状況がよくわかりますね。
「旧記」というのは鴨長明の著書『方丈記』のことです。
飢饉と火事の記事がいくつも載っています。
雇われ人の若者のおかれた状況が実感できます。
羅生門の楼上で繰り広げられる光景を思いだしましたでしょうか。
こうした類の教材が高校の教科書にはいくつも載っています。
文学国語に向けて
ぼくの机の上にはいくつかの会社で発行されている論理国語と文学国語の教科書があります。
各社がさまざまな工夫をしています。
取り上げた作品にも各社のこだわりが感じられます。
書く力や論理的な把握力、構成する力を養おうと努力している様子がよくわかります。
基本的に国語科の教師になる人は、文学の好きな人が多いようです。
批評文や論説の持つ文章にも、もちろん特筆すべき点は多々あります。
それぞれの特性を生かしていくという当初の目的は十分に果たせるものであることに違いはありません。
しかし若い時代にほとんど経験もできないような、戦争や原爆体験をはじめとして、明治の時代の人びとの感性、病的なまでに明晰な美意識に触れることの意味は十分にあると考えます。
夏目漱石『こころ』、森鴎外『舞姫』、梶井基次郎『檸檬』、志賀直哉『城崎にて』、中島敦『山月記』などの小説もぜひ省いてほしくはないのです。
そういう意味でいえば、芥川龍之介『羅生門』は必須の教材であろうと思います。
善悪の判断などは『藪の中』などの方が面白いかもしれません。
しかし扱いにくい内容であるだけに、やはり教科書には『羅生門』というのが定番中の定番なのではないでしょうか。
いろいろと書きましたが、国語という科目の魅力はまさに文学を文学の視点から読み解いていくという方向性にあると思います。
今回も最後まで、お付き合いくださり、ありがとうございました。