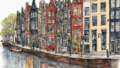武蔵野
武蔵野の冬は寒い。
空気がしんと冷えて、夜になると酒が恋しくなる。
東京府北多摩郡多摩村染谷。
今の府中市白糸台である。
村野四郎は代々酒問屋を営む家の四男として生まれた。
現在では家が建ち並び、当時の面影を残す木々も少ないが、その頃の武蔵野には雑木林がたくさんあった。
低い丘陵と点在する農家、商家。
四郎はささやかな日々の明け暮れの中に幼年時代を過ごした。
いったい東京人に郷愁はあるのだろうか。
次々と家ができ、その間をぬって道がつくられる。
近くを走る電車の音、車の騒音。
実家のあった場所にたってみても、何の感慨もわいてこない。
いや、やはり故郷には違いないという人もあろう。
生家の周囲には昔よく歩いた道がある。
木造の校舎が鉄筋になり、近くの商店がビルに変わったとしても、そこは明らかに故郷なのかもしれない。
実存の不安
村野四郎の詩はどれも実存的な人間の不安を抱いている。
ドイツ近代詩を学んだ彼は、人間の主知主義を貫いた。
「冬の抒情」という詩は、四郎の心に映った郷愁をそのまま言葉にしたものである。
渡り鳥がしずみ
地平が傾く
はじの葉が
火のようにもえ落ち
そのまま静寂
この詩にははりつめた時間が流れている。
その厳しさは他に類をみないものだ。
詩人は当時の多摩についてこう書いている。
「数多くの古墳をいだいた低い丘陵は多摩川のほとりから起こり、白い砂原や、赤い崖を露出させたりして、北方の楢や、松の雑木林の中に消えています。
その中を一筋の白い甲州街道が、庇の低い農家や、古い売薬の看板をかけた商家や、遊郭の白ちゃけた板塀などをその道筋に置いて、東から西へと長くつづいていました」
少年
武蔵野には特有の穂打唄もある。
少年だった彼の心に深く焼き付いたことだろう。
甲州街道には何が走っていたのか。
馬、牛、人力車。徒歩の人も多かったに違いない。
幼かった四郎はよく多摩川に魚をとりに行った。
川底に足がつくと、ひんやりして気持がよかった。
夏はいつも川で遊んだ。
魚たちは水の翳のように明るく輝いてみえた。
彼の目は光った。
時々痩せたイモリが足許を歩いていく。四郎はイモリが大嫌いだった。
冬の抒情
古里は花なき樹々の茂りたる
詩人ははじめ、俳句を作って荻原井泉水の層雲社にも入っている。
彼が故郷によせた気持がこの句にしみこんではいないだろうか。
花のない木々であってもよい。
魚のいない川であってもよい。
やはり故郷はある。
それはいつまでも心の中に生き続けている。
「冬の抒情」にこめられた寂寞の感情は彼が人生を真摯に生きようとしただけに、なおいっそう我々の心をうつ。
地平線の彼方に沈んでいく黄昏の夕日を、少年村野四郎は帰途につくとき、よく見たのではなかろうか。
その日から彼は人間の哀しみを知る一人の詩人であったのかもしれない。