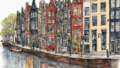童話作家・新美南吉
風光の地、知多半島。
名鉄河和線半田駅で降りると、そこは童話作家・新美南吉の故郷であった。
「わが村を南にゆく電車は、菜種ばたけや麦の丘をうちすぎ、みぎにひだりにかたぶき、とくさのふしのごとき、小さなる駅々にとまり……」と彼はこの鉄道のことを歌っている。
昼下がりの駅はどこかけだるい感じで、日差しだけが妙に強かった。
桜並木の続いた坂道を西に向かってのぼっていくと、やがて雁宿公園にたどりつく。
公園の東端からは半田の市街が一望でき、そのむこう側に海が見えた。
衣浦港である。
漁船が数隻沖合に停泊したまま、動かない。海面はいかにも初夏の暑さにうだっているように見えた。
南吉の詩碑は公園の入り口にあった。
かたつむりとランプをかたどったその碑には「貝殻の詩」が刻まれている。
かなしいときは 貝殻鳴らそ
二つ合わせて 息吹をこめて
静かに鳴らそ 貝殻を
憧れの女性
この詩は彼が中学時代、ひそかに憧れ続けた女性の思い出を綴ったものらしい。
それにしてはどことなく物悲しい響きを持った歌だ。
新美南吉は大正十二年、下駄屋と畳屋を営む家の次男として生まれた。
ところが四歳の年に母がなくなり、六歳で継母を迎える。
だが父と継母・志んとの生活はすぐに破綻した。
そこで仕方なく彼は亡き母の生家、新美家の養子となった。
しかし南吉の祖母はさしてあたたかみのある人ではなかったようだ。
「私がそばへ寄っても、私のひ弱な子供心をあたためてくれる柔らかい、ぬくいものをもっていなかった……」と、後に南吉は記している。
淋しさに耐えきれず数ヶ月で家に戻り、同じ年の暮れには継母も復籍して、異母弟をあわせた家族四人での生活が始まった。
わずか数年間の間におこったこの家庭内のいざこざが、多感な少年であった南吉の心に残した傷ははかりしれない。
彼の作品にどこか屈折した心情が見てとれるのも、幼い頃のこうした事情によるのであろう。
文学へのめざめ
中学の頃から文学に興味を持ち始めた南吉は、昭和四年、鈴木三重吉が主宰する「赤い鳥」にはじめて掲載を許され、一挙に文学への才能が花開き始めたのである。
彼は東京に出て、一心に文学を学んだ。
しかし病魔は容赦がない。
昭和十一年、初めての喀血。やがて血尿をみた。
咽頭結核であった。
療養のため帰郷したが、それでも生計をたてる必要があり、仕事をみつけなければならない。
中学時代の恩師がやっとのことで、女学校の教師の口を世話してくれた時、継母・志んは「もう明日死んでもいい」と心から喜んだという。
南吉は翌年の日記に書いている。
「ボーナスと貯金をだしてみせると、おふくろは親父を呼んだ。
ぼくはいい息子だ。
弟に十円、家にも余分に十円……」
つかの間の幸せだった。
昭和十八年、三十歳の若さで南吉は不帰の人となる。
盆踊りの季節
生家の近くには八幡社があった。
たいして大きくはないが、落ち着いた社である。
その社の裏手に離れ家がぽつんとたっていた。
南吉の亡くなった家である。
彼はこの建物の一室に閉じこもり、実家から運んでくれる食事をとる時以外は横になったままで、童話を書き続けた。
八幡社には午後の暑さがまだ残っていた。
まもなく盆踊りの季節がやってくる。
南吉の大好きだったションガイナ節を今年はいったい誰が踊るのだろうか。