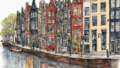信濃追分への旅
夏の盛り、信濃追分を旅した。
碓氷峠の急勾配をあえぎながら、上った汽車は軽井沢の駅に着くと、そこで多くの若者を吐き出した。
やがて浅間山が見えてきた。
中軽井沢を出たあたりから、車窓には可憐な野の花が咲き乱れている。
道造が第二のふるさととして愛した追分は、この夏も穏やかな表情を見せていた。
信濃追分は江戸時代に本陣をはじめとして、数十件の旅籠が軒を並べ、賑わいを見せていた宿場町である。
北国街道と中山道の分か去れに立って、真っ白な花ざかりの蕎麦畑などの彼方に眺めやっていると、いかにもおだやかで、親しみ深く、毎日見慣れている私の裡にまでそこはかとない旅情を生ぜしめる。
この地を心底愛した堀辰雄は、その魅力をこう書いている。
道造が中学以来の先輩であり、師と仰ぐ堀辰雄の招きで、はじめてこの地を訪れたのは、昭和九年、二十歳の時であった。
信州の風は肌に心地よい。
木々の間を渡ってくる風には、草の香りもたち混じっている。
夢はいつもかへって行った
山の麓のさびしい村に
水引草に風が立ち
草ひばりのうたひやまない
しづまりかへった午下がりの林道を
立原道造はわずか二十四年の短い生涯の間に、二冊の詩集を残した。
その詩のほとんどが油屋という旅館で書かれたものだという。
昭和十二年、脇本陣だったというこの宿は火災にあう。
この時も逗留していた道造が、土地の鳶職に助けられたという話は今も語り伝えられている。
再建された油屋は、今、国道十八号線をはずれたところに、取り残されたように建っていた。
晩年、この宿で胸の病を治していた彼は、気分のいい日、よく近くまで散策に出た。
諏訪神社や泉洞寺、あるいは芭蕉の碑のある浅間神社。
このあたりには今でも旧い追分の趣が残っている。
ソネット
吹きとばす石も浅間の野分かな
芭蕉の碑である。
しかし野の草を分けて吹く風は道造の風景ではない。
彼にはやはり夏から秋にかけての追分がよく似合う。
道造はまたこの地で、いくつかの恋も経験している。
道造の詩にこの恋が影響していることは否めない。
雲、風、草の香り……。どこか甘くそれでいてやるせない彼のソネットにしらずしらず、我々は引き込まれてしまう。
建築家・立原道造
道造は詩人である一方、別荘をつくらせれば日本一と折り紙をつけられた建築家でもあった。
設計という構成的な才能を持つ彼が、詩作において十四行詩(ソネット)という形式を確立したのも当然のことだったのかもしれない。
廃墟になった時のことまでを意識して設計図をひいていたという彼は、自分自身の肉体の崩壊を感じていたのだろうか。
昭和十三年九月からとたんに生き急ぐように旅を始めた。
九月初旬、療養先の追分から東京に戻った道造は、同月十五日、盛岡へと旅立った。
ほぼ一ヶ月滞在後、再び帰京。
十一月には長崎へと向かう。
しかし東北の旅の疲れがたたり、長崎の友人宅で発熱、数日間病臥ののち、帰京し、病院での生活が始まった。
立原の手は生きる力のない手であった。
彼は見舞いに訪れる友人に自分の手をみせては、
痩せた腕
「ぼく、こんなになっちゃいましたよ。ほらこれ見てください」と言っては痩せた腕を出してみせた。
昭和十四年三月、立原道造の短い生涯は閉じられた。
道造が死んだ時、三好達治は一編の詩をささげた。
それには人が詩人として生きるためには、聡明に清純に、そして早く死ななければならないとある。
追分の道を歩きながら、石仏や、馬頭観音をあちこちで見かけた。
高原の太陽がやさしく、木々の間から洩れていた。