 学び
学び 「蜂飼耳」詩はいつも近いところにあるのに「見たことのない風景を見たい」
詩人、蜂飼耳の世界を考えてみましょう。詩は本来どのようなものなのか。それを正確に知るためには何が必要なのか。神話の世界から平行移動しながら、現在を読み取る試みをしてみました。
 学び
学び 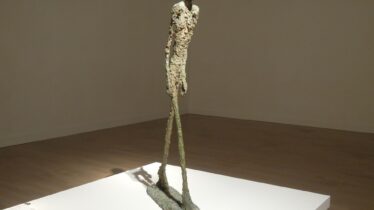 学び
学び  学び
学び  学び
学び  学び
学び  学び
学び